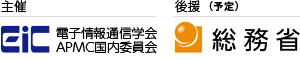- Home
- マイクロウェーブワークショップ
- ワークショップ プログラム
- 11月26日 (水)
ワークショップ プログラム
11月26日 (水)
WE1A 開会式
11月26日 (水) 10:00-10:10 Room 1+2 (アネックスホール F201+F202)
実行委員長挨拶
大久保 賢祐 (岡山県立大学)WE1A 基調講演 1
11月26日 (水) 10:15-11:05 Room 1+2 (アネックスホール F201+F202)
電波政策の動向について
Trends in Radio Frequency Policies in Japan小川 裕之 (総務省 総合通信基盤局 電波部 電波政策課長)
電波は今や、デジタル社会の成長基盤となっており、電波の有効利用を図りつつ、電波利用による新たな技術の導入や新たなビジネス展開を促進していくことが求められている。
本講演では、電波利用ニーズが急速に増加する中、有限希少な国民共有の財産である電波の一層の有効利用促進のための電波政策についての最新動向を紹介する。
→ 代表的なスライドをご覧いただけます (PDF)
本講演では、電波利用ニーズが急速に増加する中、有限希少な国民共有の財産である電波の一層の有効利用促進のための電波政策についての最新動向を紹介する。
→ 代表的なスライドをご覧いただけます (PDF)
 略歴:
略歴:1998年 郵政省入省。
放送技術課技術企画官、東北大学電気通信研究所特任教授、研究推進室長、宇宙通信政策課長、移動通信課長を経て、令和7年7月より現職。
WE1A 基調講演 2
11月26日 (水) 11:10-12:00 Room 1+2 (アネックスホール F201+F202)
IOWN時代に向けた無線アクセス技術の新たな展開
Toward the Future of Wireless Access in the IOWN Era鷹取 泰司 (NTT(株) アクセスサービスシステム研究所、南山大学 理工学部 教授)
将来の無線アクセスにおいては、無線通信はスマートフォンでのインターネット利用だけではなく、あらゆる産業でのデジタルトランスフォーメーションを推進していく役割を期待されています。IOWN (Innovative Optical and Wireless Network) 時代には遠隔地点がダイレクトにつながり、空間を超えた連動による価値創造が期待されています。
本講演では本格的なIOWN時代に向けた無線アクセスの新たな展開についてご紹介いたします。
→ 代表的なスライドをご覧いただけます (PDF)
本講演では本格的なIOWN時代に向けた無線アクセスの新たな展開についてご紹介いたします。
→ 代表的なスライドをご覧いただけます (PDF)
 略歴:
略歴:1993年 東北大・工・電気卒。
1995年 同大学大学院情報科学研究科修士課程修了。
同年、日本電信電話(株)入社。以来、空間信号処理、高速通信システムの研究開発に従事。
2004〜2005年 デンマークオールボー大学客員研究員。
2005年 博士(工学)(オールボー大学)。
2009〜2010年 IEEE802.11 TGac COEX ad-hoc 共同議長。
現在、南山大学理工学部電子情報工学科教授。NTTアクセスサービスシステム研究所客員上席特別研究員。電波産業会無線LANシステム開発部会委員長
WE1B 基礎講座
11月26日 (水) 14:00-16:00 Room 1+2 (アネックスホール F201+F202)
移動通信について基礎から学びなおしましょう!
Let's Re-Learn the Fundamentals of Mobile Communications !オーガナイザ / 座長 : 山中 宏治 (三菱電機(株))
わが国では2020年に第5世代移動通信 (5G) のサービスが始まり、2030年頃からのサービス開始が予想されている6Gに向けた研究開発が盛んに行われている。非常に多くのエンジニアやマイクロ波関係者が5Gあるいは6Gに関わる研究開発や事業開拓に携わっているのだが、果たしてどれくらい移動通信についてきちんと理解しているだろうか。自分の専門技術分野については理解している人も移動通信の全体像については理解できていないところが多いのではないだろうか。
5Gのさらなる発展と6Gに向けた研究開発の加速が期待されるこのタイミングで、移動通信の基礎を学びなおす機会を提供するため、エリクソン・ジャパンにてCTOを務め、ケータイWatch「モバイル技術百景」連載など多くの執筆活動を進めておられる藤岡様に移動通信関係者が最低限理解しておくべき事柄を紹介してもらう。本基礎講座を受講することで自分が理解できていたことと理解できていなかったことを見つめなおし、移動通信に関する基礎的力量をレベルアップされることを期待する。
キーワード : 移動通信、基地局、5G、6G、コアネットワーク
5Gのさらなる発展と6Gに向けた研究開発の加速が期待されるこのタイミングで、移動通信の基礎を学びなおす機会を提供するため、エリクソン・ジャパンにてCTOを務め、ケータイWatch「モバイル技術百景」連載など多くの執筆活動を進めておられる藤岡様に移動通信関係者が最低限理解しておくべき事柄を紹介してもらう。本基礎講座を受講することで自分が理解できていたことと理解できていなかったことを見つめなおし、移動通信に関する基礎的力量をレベルアップされることを期待する。
キーワード : 移動通信、基地局、5G、6G、コアネットワーク
※タイトルをクリックすると、アブストラクトが閲覧できます
- 1 これだけは知っておきたい移動通信の基礎
- Fundamentals for Mobile Communications
藤岡 雅宣 (XGMF)
WE3B ワークショップ
11月26日 (水) 14:00-16:00 Room 3 (アネックスホール F203)
テラヘルツ通信に向けたデバイス開発の最前線
Advanced Device Technologies for Terahertz Communicationsオーガナイザ / 座長 : 笠松 章史 ((国研)情報通信研究機構)
無線通信の大容量化に向けて、テラヘルツ帯の周波数の活用が期待され、様々な研究開発が実施されているが、デバイス技術については依然として様々な課題が存在している。とくに、通信距離の確保、低位相雑音の基準信号源、超高周波に対応したパワーアンプ、低消費電力化は、解決すべき大きな課題である。
本セッションでは、これらの課題の解決に向けたデバイス開発を実施している皆様を講師にお招きし、開発の最先端について紹介する。
キーワード : テラヘルツ、フェーズドアレイ、集積型光周波数コム、サブテラヘルツ帯パワーアンプ
本セッションでは、これらの課題の解決に向けたデバイス開発を実施している皆様を講師にお招きし、開発の最先端について紹介する。
キーワード : テラヘルツ、フェーズドアレイ、集積型光周波数コム、サブテラヘルツ帯パワーアンプ
※タイトルをクリックすると、アブストラクトが閲覧できます
- 1 300GHz帯フェーズドアレイの高集積化に向けたCMOS設計技術
- CMOS Design Techniques for Highly Integrated Phased Arrays in the 300-GHz Band
藤島 実 (広島大学)
- 2 集積型光周波数コムで切り拓くテラヘルツ波フォトニクス
- Exploring Terahertz Photonics Enabled by Integrated Optical Frequency Combs
鐵本 智大 ((国研)情報通信研究機構)
- 3 化合物半導体を用いたサブテラヘルツ帯パワーアンプ向け電子デバイス
- Compound Semiconductor-Based Electronic Devices for Sub-THz Power Amplifiers
多木 俊裕 (富士通株(株))、中舍 安宏 (1FINITY(株))
WE4B ワークショップ
11月26日 (水) 14:00-16:00 Room 4 (アネックスホール F204)
空間伝送型ワイヤレス電力伝送システム最前線 (制度化 / 製品化 / 研究開発)
Frontiers of RF-Beam Wireless Power Transfer System (Institutionalization, Productization and R&D)オーガナイザ : 勝永 浩史 (丸文(株)) 座長 : 藤野 義之 (東洋大学)
2022年の省令改正により、マイクロ波を用いた空間伝送型ワイヤレス電力伝送システム (RF-Beam WPT) の実用化が可能になり、3年が経過した。IoTデバイスへの給電技術の一手段として期待が高まる中、RF-Beam WPT の製品化・市場導入も進みつつあり、この技術の更なるステップアップに向けて、各方面で研究開発が取り組まれている。
今後の制度化の最新動向、ビジネス展開をふまえた製品開発・社会実装に取り組む企業の最前線を紹介するとともに、我が国のエネルギー安全保障の一役を担う可能性のある未来に向けた研究開発の最前線を紹介する。
キーワード : マイクロ波、ワイヤレス電力伝送、ワイヤレス給電、RF WPT、RF-Beam WPT、制度化、IoT、ドローン、宇宙太陽光発電
今後の制度化の最新動向、ビジネス展開をふまえた製品開発・社会実装に取り組む企業の最前線を紹介するとともに、我が国のエネルギー安全保障の一役を担う可能性のある未来に向けた研究開発の最前線を紹介する。
キーワード : マイクロ波、ワイヤレス電力伝送、ワイヤレス給電、RF WPT、RF-Beam WPT、制度化、IoT、ドローン、宇宙太陽光発電
※タイトルをクリックすると、アブストラクトが閲覧できます
- 1 空間伝送型WPTシステムの国内制度化と制度化に向けた研究開発
- Institutionalization of the Beam-WPT System in Japan and Research and Development for Institutionalization
関野 昇 (電気興業(株))
- 2 グローバルに展開される920MHz帯ワイヤレス給電システムの応用事例
- Driving Global Adoption of the 920MHz WPT System
津持 純 (エイターリンク(株))、田中 勇気 (パナソニックホールディングス(株))
- 3 ワイヤレス給電によるオフグリッドIoTの高度化利用
- Advanced use of Off-Grid IoT by Wireless Power Transfer
古川 実、堀内 普一郎、岩崎 徹、寺嶋 正紀 ((株)Space Power Technologies)
篠原 真毅 (京都大学)
WE5B ワークショップ
11月26日 (水) 14:00-16:00 Room 5 (アネックスホール F205)
EMC対策にAIをどう活かす? ノイズ予測と設計支援の可能性
How Can AI Be Utilized to EMC Design and Countermeasures? — Possibilities in Noise Prediction and Design Support —オーガナイザ / 座長 : 室賀 翔 (東北大学)
AI技術の導入は、電磁環境両立性 (EMC) 分野において急速に進展しており、ノイズ源の特定、近傍磁界分布の推定、高精度な伝搬経路の予測、さらには吸収体やシールド構造などの対策部品の最適化に至るまで、設計・評価プロセス全体に応用されつつある。
本セッションでは、EMC設計への機械学習の応用技術について、「ノイズ予測」「設計最適化」の2つの視点で整理し、機械学習や最適化アルゴリズムを用いたEMC設計・評価支援の最新事例を紹介する。研究と産業応用の両視点から、機械学習がもたらすEMC設計および対策技術革新の可能性と課題について議論する。
キーワード : 電磁環境両立性(EMC)、AI / 機械学習、ノイズ源推定、放射ノイズ予測、シールド設計、材料設計
本セッションでは、EMC設計への機械学習の応用技術について、「ノイズ予測」「設計最適化」の2つの視点で整理し、機械学習や最適化アルゴリズムを用いたEMC設計・評価支援の最新事例を紹介する。研究と産業応用の両視点から、機械学習がもたらすEMC設計および対策技術革新の可能性と課題について議論する。
キーワード : 電磁環境両立性(EMC)、AI / 機械学習、ノイズ源推定、放射ノイズ予測、シールド設計、材料設計
※タイトルをクリックすると、アブストラクトが閲覧できます
- 1 近傍磁界情報の機械学習を用いたPCB上のノイズ源推定
- Estimation of Noise Sources on Printed Circuit Boards using Machine Learning of Magnetic Near-Field Information
田中 元志、鴨澤 秀郁 (秋田大学)
- 2 車載機器の放射ノイズを予測する機械学習モデル
- Machine Learning-Based Prediction of Radiated Emissions in Automotive Electronics
末永 寛 (パナソニック インダストリー(株))
- 3 AIを用いたシールド設計支援 — NGnetを用いたトポロジー最適化によるFSSの最適設計 —
- AI-Aided Shield Design — Optimal Design of FSS using Topology Optimization with NGnet —
萓野 良樹 (電気通信大学)
室賀 翔 (東北大学)
WE6B ワークショップ
11月26日 (水) 14:00-15:30 Room 6 (アネックスホール F206)
アンテナシミュレーション最新技術 — スパコンからモデリング技術まで —
Latest Antenna Simulation Technology — From High Performance Computing to Modelling Techniques —オーガナイザ / 座長 : 有馬 卓司 (東京農工大学)
アンテナシミュレーションの需要はますます高まっている。一方、シミュレーションしたい問題は大型化および複雑化が進んでいる。
本セッションでは、現代のアンテナシミュレーションに必要となる、大型計算機 (いわゆるスーパーコンピュータ) がどこまでできるか、今後の大型計算機の予測からシミュレーション技術および、シミュレーション対象の最新モデリング技術まで説明する。
キーワード : シミュレーション、大型計算機、電磁界解析、FDTD法、モデリング技術
本セッションでは、現代のアンテナシミュレーションに必要となる、大型計算機 (いわゆるスーパーコンピュータ) がどこまでできるか、今後の大型計算機の予測からシミュレーション技術および、シミュレーション対象の最新モデリング技術まで説明する。
キーワード : シミュレーション、大型計算機、電磁界解析、FDTD法、モデリング技術
※タイトルをクリックすると、アブストラクトが閲覧できます
- 1 今のスパコンにできること、未来のスパコンに期待できること
- What Supercomputers can do Today, What We Expect in the Future
河合 直聡 (東北大学)
- 2 地中レーダによる水道管漏水検出のFDTDシミュレーション — 水道管漏水のモデリング —
- FDTD Simulation of Water Pipe Leakage using Ground Penetrating Radar — Modeling of Water Pipe Leakage —
園田 潤 (仙台高専)
- 3 最新の時間領域シミュレーション技術
- Latest Time Domain Simulation Technology
有馬 卓司 (東京農工大学)
WE7B 超入門講座
11月26日 (水) 14:00-15:30 Room 7 (展示ホール ワークショップ会場)
初心者向け 90分で分かるアンテナと伝搬 〜基本・使い方・測り方〜
Antennas and propagation for beginners in 90 minutes — Fundamentals, Applications, and Measurements —オーガナイザ : MWE 2025 展示委員会 座長 : 杉山 勇太 (三菱電機(株))
近年、携帯電話やスマートフォンが普及し、無線通信が身近なものになっている。一方、アンテナは無線通信には欠かせない重要な構成要素であるが、いざ設計するとなると、その敷居が高いと感じている技術者が多くいると思われる。
本講座では、これまでアンテナに携わってこなかった技術者を主な対象とし、基本的なアンテナの種類やその特性を述べるとともに、アンテナ設計や測定について事例を交えながらわかりやすく解説する。
キーワード : アンテナ、電波伝搬、放射パターン、指向性、利得
→ 代表的なスライドをご覧いただけます (PDF)
本講座では、これまでアンテナに携わってこなかった技術者を主な対象とし、基本的なアンテナの種類やその特性を述べるとともに、アンテナ設計や測定について事例を交えながらわかりやすく解説する。
キーワード : アンテナ、電波伝搬、放射パターン、指向性、利得
→ 代表的なスライドをご覧いただけます (PDF)
※聴講者には講演スライドの印刷物を無料で配布します (事前・事後のデータ配布はありません)。
- 1 アンテナの基礎知識
- Basic Knowledge of Antennas
秋元 晋平 (三菱電機(株))
- 2 アンテナ設計・測定・電波伝搬
- Antenna Design, Measurement and Propagation
柳 崇 (三菱電機(株))
- 3 総括的討論
- Comprehensive Discussion